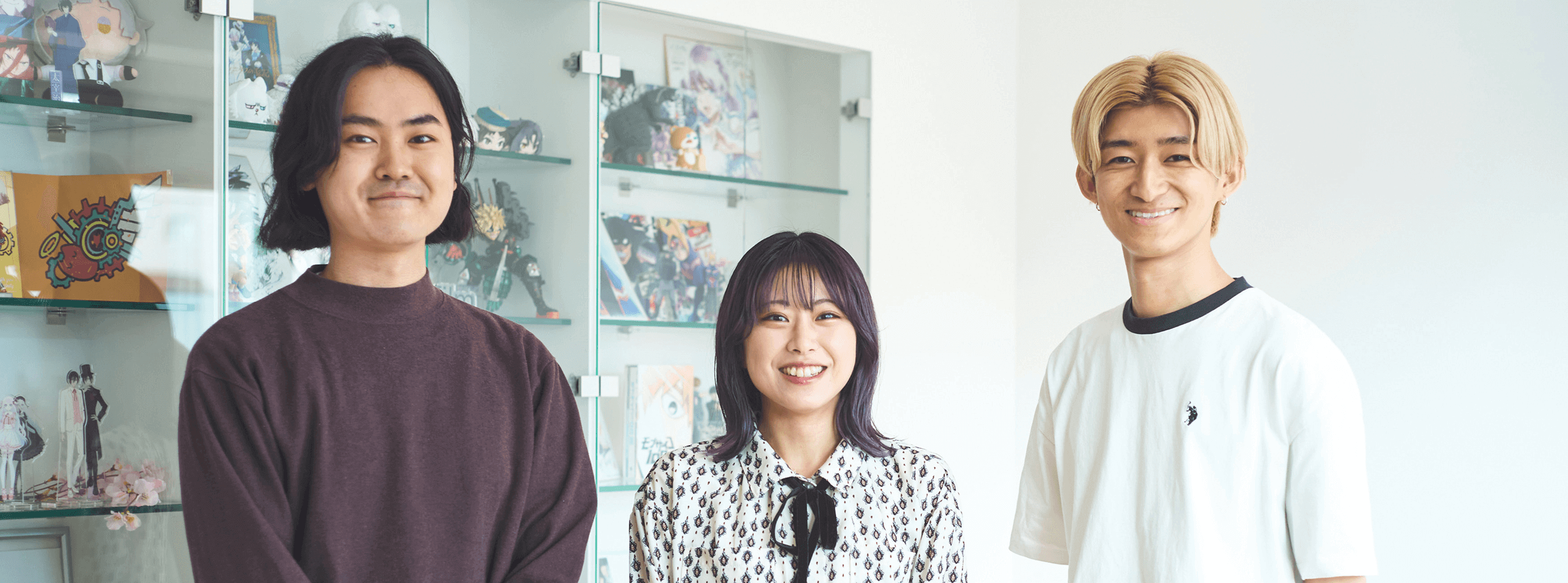アニメ制作の入口である「制作進行」からのキャリアアップに向けて
――アニメーター志望ではない限り、多くの人が制作進行からキャリアを始めると思います。大薮さんご自身もそうだったと仰っていましたが、そこからどのようにキャリアアップしていくのでしょうか?
大薮芳広:その時の制作状況やその人の適正にもよりますが、制作進行を3年から5年ほど務めたら、演出志望の方は設定制作になり、プロデューサー志望の方は制作デスクになる。制作デスクとして2、3作品を担当して、早ければ30歳手前でプロデューサーになるというのが基本的なキャリアアップです。
ところが昨今では、制作に携わる人間としていろんな作品を経験することが難しくなってきています。今は1スタジオが1年間に制作できる作品数が減ってきているからです。
――それはなぜでしょうか?
大薮芳広:働き方改革によって(昔に比べて)1人あたりの就労時間が短くなっていることと、作品に求められるクオリティレベルが上がり、アニメーションの密度が高くなっていることが理由です。各セクションとも人を増やしていますが、それでも制作期間が長くなる。
企画が実際にアニメとして完成するまでの時間も昔とは全然違うんですよね。以前はプリプロ1年、実制作1年と、あわせて2年で制作・放送していたものが、制作期間が長くなって4年くらいかかってしまう。監督ら主要スタッフもお忙しくて、お願いできるのが何年後、という方もいらっしゃる。ボンズフィルムで今動いている企画の中には、2029年放送予定のものもあったりします。
しっかりした制作体制で時間をかけて作っていく流れは良いことですが、制作に携わる人間にとっては「いろんな作品に携わって経験を積む」ということが難しくなっているのが課題ですね。
私が制作進行をやっていた頃は、年間テレビTVシリーズを7、8話数担当していました。タイトル違いも受け持って経験値を積んできましたが、今は、制作進行が担当できる話数は年間で2話。忙しい時期に入社した人でも、年間3話程度です。
――ボンズフィルムでは、そうした課題にどのように向き合っているのでしょうか?
大薮芳広:制作の役職を細分化し始めています。作品ごとに「制作進行」を6人程度配置して、さらに「制作進行チーフ」「制作デスク補佐」「制作デスク」、そして「AP(アシスタントプロデューサー)」「ラインP(プロデューサー)」をつけて、「プロデューサー」がいる、という制作体制にしています。役職を少しずつ分けて、ひと段階ずつステップアップできるようにしています。そして役職ごとにゴールを作って、いろいろな経験を積めるようにしていこうという取り組みをしています。

「早くプロデューサーになりなさい」と新卒に必ず伝える理由
――制作進行を専門職にする、というのはあまりないのでしょうか?
大薮芳広:制作進行を専門職として続ける方も稀にいらっしゃいますが、ボンズフィルムはオリジナル作品を作る会社なので、作品づくりの企画段階から関われるプロデューサーに育ってほしいと考えています。そのため、制作進行として入社した制作志望の方には、必ず「早くプロデューサーになりなさい」と伝えています。何歳でどんなポジションに行きたいのか、どんなキャリア形成をするかを自分で考えることの重要性を、ボンズフィルムではまずお話しします。
新卒の人たちには、いつもこう話しています。「君たちは制作進行からのスタートだけど、テレビ局やメーカーの人は、入社したらすぐにプロデューサーになる人もいます。もし君が35歳でようやくプロデューサーになった時、20代からプロデューサーをしている人たちの輪の中に入って、より視聴者に近い若い目線での企画やクリエイティブをしていけますか?」と。
――なるほど、一緒に作品を作っていく社外プロデューサーとの年齢差ができてしまうと。
大薮芳広:だから社外の方たちと同世代のうちに、早くプロデューサーになってほしいんです。また、若くしてプロデューサーになると、自分と同期のスタッフと一緒に成長することもできます。例えば、自分が制作デスク、プロデューサーになった時に、同期の作画スタッフを作画監督、キャラクターデザイナーとして起用できれば、同じものを見て育った、同じ世界観を共有できる同世代のスタッフと一緒に作品を作っていくことができます。それは、あとから得ようと思っても得られない経験になります。

ボンズフィルムが描く、未来への地図
――ボンズフィルムとしては、5年後、10年後にどういう会社になっていたいとお考えでしょうか?
大薮芳広:今はまだ新会社としてスタートしたばかりなので、お話ししてきた通り、「ボンズらしさを継承していく」ことを目標にしています。ただ、私は個人的には、将来はもう少し柔軟にジャンルの幅を広げていければとも考えています。例えばボンズでは、『桜蘭高校ホスト部』や『赤髪の白雪姫』といった少女漫画原作のものを作ったり、子ども向け作品も作ったりしています。皆さんの中には「ボンズ」が制作する作品のイメージを持っている方もいると思うのですが、その中に意外性がある作品もラインナップされると良いなと思っています。
――“ボンズらしい作品”というのは長年積み上げてきたブランド力でもあると思いますが、そこからさらに広げていきたいと。
大薮芳広:ボンズフィルムは各スタジオが自分たちで運営する独立採算制を採っていますが、ボンズフィルム全体として見た時には、実はどのスタジオも作品の規模感やカラーが横並びに見えてしまったりもするんです。スタジオ同士であまりにカラーが違う作品を制作すると、予算も全く違ってくるので、スタジオ間で上手く住み分けできなかったり、公平感を欠いたイメージになったりもします。
例えば子ども向けの作品は、ボンズフィルムでやりたいと思っても企画を通すのがなかなか難しい。なぜなら他のものと比べると予算の規模が大きく違ってくるし、国内外のお客様が考えるブランドイメージとも大きく乖離してしまう、といった両面のハードルがあるからです。
少女漫画やギャグものは、たまにできる。けれども子ども向け作品はなかなか定着しにくいというのが実状です。そんな中で、ブランドを拡張させるという意味では、『運命の巻戻士』の制作をさせていただけることは本当にありがたいことだと思います。
ちなみに、もう亡くなってしまったのですが、ボンズの取締役だった逢坂浩司というスーパーアニメーターが、子ども向け作品をすごくやりたがっていて、その走りが2000年から放送された『機巧奇傳ヒヲウ戦記』でした。
ボンズフィルムでは、これまで多くの方が積み上げてきてくださった「ボンズらしい作品」は継承しつつ、そこに、何か違うエッセンスを加えてくださる方が来て、会社と一緒に成長していけたら良いなと思います。この先、企画を作っていくのは、私ではなくて若いプロデューサーたちなので。期待しています。