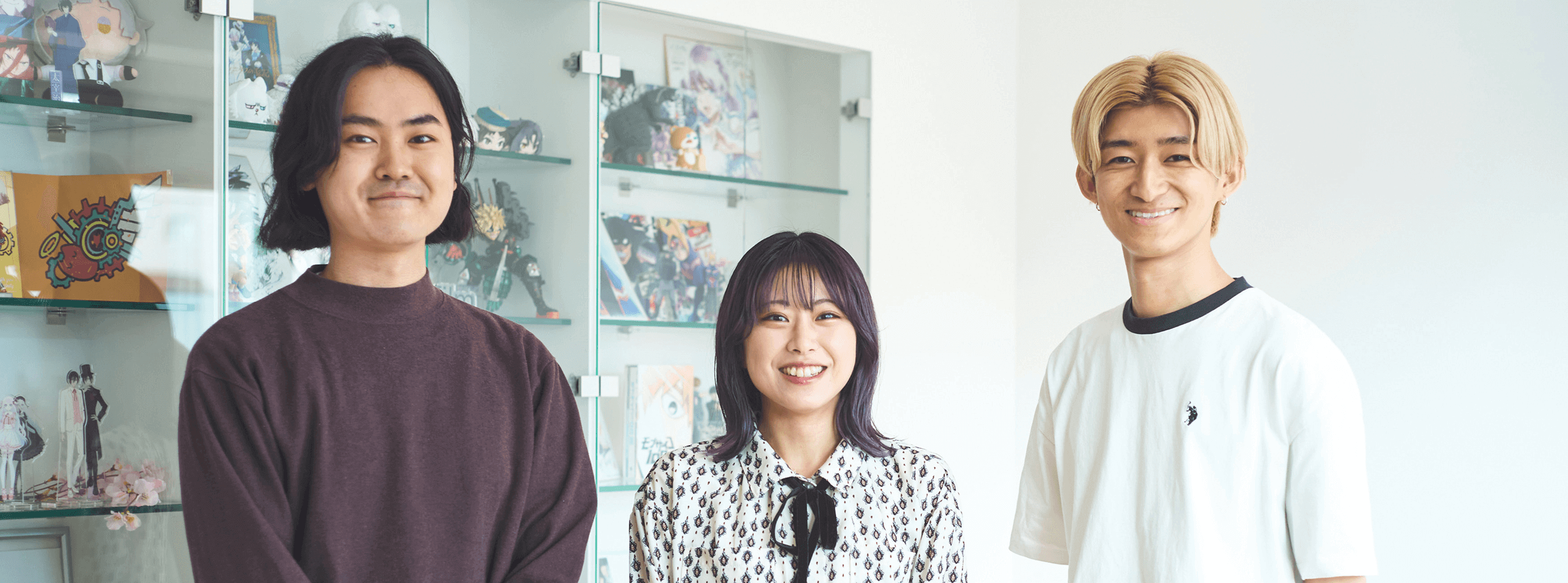22万人を超えるクリエイターに利用されるポートフォリオサービス「foriio」で、新たに、アニメ制作会社とクリエイターとの健全なマッチングのために、企業と個人を橋渡しするための「クリエイティブの現場から - Inside the Studio - 」シリーズが立ち上がった。
その初めてとなる特集に迎えたのは、数々の骨太なオリジナルアニメを生み出してきた、アニメ制作会社ボンズだ。特に、アニメ制作の礎を担う「制作進行」職にフォーカスしている。
ボンズと言えば、2024年に、制作部門を独立させたボンズフィルムを設立している。
2025年現在は、『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONや『ガチアクタ』を制作・放送中だ。そして、2度に渡るテレビアニメシリーズと2作の劇場版を制作してきた『鋼の錬金術師』以来となる荒川弘氏とのタッグによる『黄泉のツガイ』や、「少年ジャンプ+」連載の人気作『マリッジトキシン』が2026年に放送公開を控えている。さらに、松本理恵氏を監督に迎えた、『月刊コロコロコミック』連載の『運命の巻戻士』アニメ化にも大きな期待が寄せられている。
そんな最中にあっての、ボンズ初となる新会社設立。サンライズで『機動武闘伝Gガンダム』『カウボーイビバップ』などを担当していた南雅彦氏や主要スタッフが中心となってボンズが設立された1998年以来の、大きな動きとも言える。
今回、ボンズの取締役にして、新会社ボンズフィルムの代表取締役を務める大薮芳広氏の口から、その設立の経緯と真意が初めて明かされる。
取材・執筆:渡辺由美子 撮影:小野奈那子 編集:押剣山

大薮芳広
株式会社ボンズの取締役。2024年設立の株式会社ボンズフィルムでは、代表取締役も務める。制作進行からプロデューサーとなり、現在もスタジオを受け持っている。代表作は『STAR DRIVER 輝きのタクト』『DARKER THAN BLACK』シリーズ。今は『僕のヒーローアカデミア』『ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を担当。現在、『黄泉のツガイ』『マリッジトキシン』『運命の巻戻士』を準備中。

ボンズがスタジオごとに独立採算制を採用する理由
――大薮さんの観点から、ボンズという会社の特徴をお聞かせください。
大薮芳広:ボンズの特徴というのは、「スタジオ制」と言われるような、1つのスタジオごとに1つの作品を受け持つ制作体制にあります。1つの作品を作るのに必要な制作ラインをプロデューサーが持っていて、そのスタジオの中で作品制作が完結するようにできています。
そしてこれは、ボンズの創業代表である南雅彦が確立した基本方針として今も続いているのですが、各スタジオごとに独立採算制を採っています。作品を制作する際には、スタジオのプロデューサーがその作品の予算を立案する。通常であれば、各作品の制作費は一旦会社に集めて、そこから各スタジオに配分していく方法がスタンダードだと思います。ですが、ボンズではスタジオごとに予算も違えば“財布(=制作資金と管理)”も違い、「各スタジオが作品ごとに予算を管理し、作品として独立した利益を出す」ことを目標にしています。
――各スタジオを独立採算制で運営しているのはなぜでしょうか?
大薮芳広:スタジオごとに財布を分けることで「その作品のためにお預かりしたお金を100%に近い形で画面に投入する」ということができるからです。スタジオごとの財布を明確化することで、作品にも出資者の方に対してもフェアな形を採りたい、という考え方ですね。
もうひとつは、プロデューサーの独立心や責任感の向上を見込んでいます。単に会社から与えられた予算に応じた作品を作ろうというのではなく、作品を良くしながらも時には自分たちがかき集めてきた予算内でどうやって作品を良くして売上も上げるかを考える。プロデューサーが自分で財布を管理すれば、もしこのパートのスケジュールが伸びたらどれくらい余計にお金がかかってしまうのか……といったことも実感できる。予算管理に対して鋭敏になれますよね。
1作品ごとに数億円をお預かりしているので、各プロデューサーがそれを理解しながら制作に臨むことも独立採算制の目的です。アニメ制作会社の基本は「製造業」であって、だからこそ制作費の中で利益を出すことを一番の目標にしていますし、その意識を持つことは大切だと思います。

「黄泉のツガイ」
財布は別。だけど、スタジオ間の連携を強めるために
――1作品ごとに財布が違うというのはユニークですね。けれども作品ごとに収益の規模や種類も相当違ってくるかと思います。
大薮芳広:そうですね。大前提として、アニメにおいて、制作費だけで潤沢な利益を出すことはかなり難しい。うちは予算を画面に100%、全力投球してしまいがちな会社でもあります。ですので、実際には赤字になることもあります(苦笑)。
そのため、ボンズでは昔から「二次利用」(配信や商品化等)から受け取れる利益を重要なものと考えてきました。作品がヒットするスタジオもあれば、赤字が出るスタジオもありますが、二次利用の利益によってスタジオを維持することができ、新しい作品や新しい才能が生まれる。「より作り手に還元されるべき」というボンズの方針からそうなっています。
――制作費が完全に分かれていると、スタジオごとの個性が強く出る一方、それぞれの独立性も強まってしまうのではないかと思うのですが、その点はどうでしょうか?
大薮芳広:たしかに、スタジオをあまりに分離すると独立独歩になりすぎて、同じ会社にも関わらずスタジオ同士で同じ人材の取り合いなども起こってしまいます。自分のスタジオで手一杯で、他のスタジオのことは何も知らない、というケースも業界ではよく聞く話です。だからボンズでは、各スタジオが独立しつつも連携が取れる環境作りをしています。
具体的には、どのスタジオも基本的には同じビル、同一のフロアで仕事をしています。そうすると、スタジオ間での横の繋がりも自然にできます。例えば制作進行が別のスタジオの制作進行に「なんか大変そうだね。手伝えることある?」みたいに声をかけることもありますし、スタジオ間で制作進行やスタッフの応援のための短期異動もよくあります。誰もが自分の作業を抱えているので、遅れたり上手くいかない時もあります。そんな時も声かけをすることで安心感も生まれるし、トラブルになりそうな事態が起きてもカバーできる。そういう助け合いも頻繁に行われています。
独立採算性を採りながらもスタジオ間の連携を強める。こうしたことが、南が作ったボンズらしさだと私は考えていて、その理念を引き継いで加速させるためにボンズフィルムを設立しました。

風通しを良くするためにこそ、ボンズフィルムが生まれた
――2024年に、ボンズから新会社「ボンズフィルム」が生まれたのはどういう経緯なのでしょうか?
大薮芳広:私の中ではボンズは新しい会社だという感覚なのですが、1998年の設立から気付けばもう30年近く経っています。最初は5人、10人で始めた会社が、今は従業員が100人以上と、多くの方に在籍していただけるようになりました。
ただ、大所帯になると、ボンズの良さである密なコミュニケーションが難しくなってきます。そこで現場の空気を保ちつつ風通しを良くするために、本社機能と制作機能を切り分けて制作に特化させるべく、ボンズフィルムとして、アニメの制作部門を独立させることにしました。そのため今もボンズフィルムの制作、クリエイター、プロデューサーと近いままでいられています。逆に、私との距離が近すぎてこれはこれでどうなのだろうと思うところもありますが……(笑)
――今後、制作部門の採用は、ボンズフィルムとしてされるのでしょうか?
大薮芳広:現状では、ボンズで採用してボンズフィルムに出向してもらうという形になっています。理由としては、福利厚生面からです。新会社としてしっかり整備してから、ボンズフィルムとして採用していく形になります。