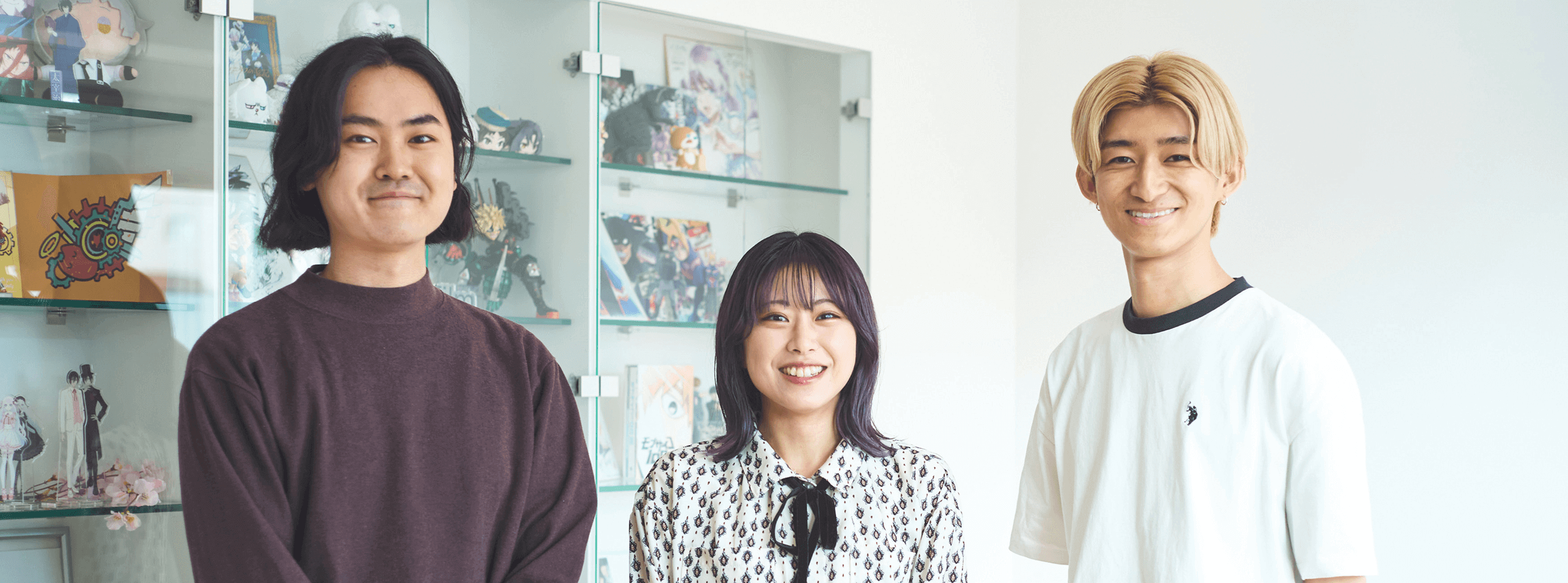「僕のヒーローアカデミア」
独立系のスタジオだからできる、オリジナル作品への果敢な挑戦
――ボンズフィルムではどのような作品を作っていこうとお考えですか?
大薮芳広:ひとつは原作ものです。大切な原作をお預かりしているのですから、それに対してボンズ同様、誠実に向き合っていこうと考えています。ありがたいことに、ボンズ時代から長く制作させていただいているタイトルも多く、今期で言うと、『僕のヒーローアカデミア』もそうです。ボンズフィルムとしても、『ガチアクタ』が始まりました。
そしてもうひとつの軸は、やっぱりオリジナル作品です。
――ボンズでは昔から、オリジナル作品に力を入れていますよね。
大薮芳広:ボンズは、現在に至るまで独立系のスタジオです。近年は、アニメ制作会社がテレビ局や出版社、映画会社の傘下に入ることも多いので、独立資本のスタジオというのは少し珍しくなったかもしれません。なぜ独立の道を選んだのかというと、「自分たちでやりたい作品を選ぶ」ことができるからです。「好きなものを作れる会社」の究極は、「オリジナル作品に注力する会社」だと思います。スタッフと一緒にいちから作っていけるタイトルを作り続けるべきだなと。これもボンズ時代からの基本理念でもあり、今後もボンズフィルムとして継承していきます。
ゼロからオリジナル作品を作ることは、スタジオにとって、そして原作ものを作る上でも大切なことです。監督、シナリオライター、プロデューサーの頭の中にある漠然としたまだ見ぬ答えを具現化していくためには、プリプロ(企画から絵コンテまでの、作品の準備工程)段階からキャラクターデザイナーなど多くの人の力が必要になります。そうしたゼロからイチにする作業を、みんなでやる。また、ある程度全体の構造ができたとしても、次は各話のビジョンが必要になる。まだ見ぬ各話の全体像を、制作進行が各セクションのスタッフや演出さん、作画監督さんたちと一緒に作っていく必要がある。
そのためには「この物語はこういう内容で、この話数はこういう話なんだ」ということをみんなで共有しないといけない。私自身もオリジナルを何本も作りましたけど、意識もテンションもみんなで共有する作業というのは、めちゃくちゃ大変なんですよ。
――それほど大変だけれども、ボンズフィルムさんはやっぱりオリジナル作品を作るのですね。
大薮芳広:その難しいハードルをみんなで乗り越えることで、スタジオの体力が上がりますからね。プロデューサーの人間力も上がる。スタジオに体力がつくと、原作を預からせていただいた時に、より良い作品にできて原作にお返しができるようになります。完成した映像だけではなく、個人のスキル、スタジオの体力、それぞれが財産になっていくということなんです。
――スタジオの体力がつけば、現場全体としてアニメ制作をする力も強くなり、原作ものも含めて各作品にフィードバックされると。
大薮芳広:はい。ボンズでは、企画会議があったんですが、トップダウンではなくて、現場スタッフの方からボトムアップで企画が上がってくるケースがかなり多かったです。他社さんの話を聞くと、トップダウンで降ってきた企画をやらないといけない場面がどうしても増えてくるそうですが、ボンズではそうはならない、独立資本であることの強みですよね。そうして現場から上がってきた企画を、プロデューサーも制作デスクも、制作進行もみんなで忌憚のない意見を出しながら検討していく。その熱気を、ボンズフィルムでも継承しています。

「交響詩篇エウレカセブン」
「クリエイターファースト」というボンズの伝統
――ボンズには凄腕のクリエイターの方が集まっていますが、どのような理由や仕組みがあるのでしょうか。
大薮芳広:ボンズには、長年一緒に作ってくださっているクリエイターの方が多いのも特徴です。なぜなら、私たちはオリジナル作品を作りたい会社なので、ゼロから一緒に作ってくださるクリエイターがいないと成り立たない。そのためにも、創業時から「クリエイターファースト」という方針を採っています。クリエイターがやりたいことをどうやって通すか。そしてクリエイターをどう守るか。例えばクライアントからのリクエストがクリエイターのモチベーションを下げかねない時、私たちが整理して、やりたいことを損なわないものにしたり、ダメージが少ない形で伝えたりするようにしています。おそらくどこの会社の制作の方もしていることとは思いつつ、クリエイターファーストの意識は特に強い会社だと思っています。ボンズフィルムも、オリジナル作品にぜひ参加したいというクリエイターの方が集まれる場所でありたいですね。
――アニメの実制作をするクリエイターの方は現在、どの程度社員化されているのでしょうか。特にアニメーター職である3DCG部門や手描きの2D作画についてお聞かせください。
大薮芳広:3DCG部門については、新卒から育成して100%社員化しています。2D作画は、歴史が長い分、いろんな方がいらっしゃいます。もちろんフリーランスの方もいらっしゃいますけれども、ひと昔前より社員の割合が増えました。新人は社内で育成をしています。研修を含めて育成期間を設けて、そこで合格すれば社員として採用するケースもあります。以前からの作画スタッフの方も、ご本人の希望や適正に合わせて社員になっていただいています。福利厚生という面から、社員を望む方も増えてきています。一方で、監督や演出家、脚本家などは基本的にフリーランスの方になりますね。

作品の礎を作る「制作進行」という仕事は、やりがいに満ちている
――現在、特に募集に力を入れているのが、「制作進行」職だと伺いました。そもそも、制作進行とはどんな仕事でしょうか。
大薮芳広:1本のアニメにおいて、自分で特定の話数を担当して、各セクションのパートごとに、どのクリエイターさんに何をお願いするかを決めて、実際にお願いしてそれを作ってもらうまでも含めて、現場をコーディネートする仕事です。制作進行の仕事として、どのアニメーターさんを手配しどこをお願いするかというのは非常に重要です。例えば1話300カットぐらいあったとして、15人から20人ほどのスタッフでやると15カットか20カット刻みくらい。それを振り分ける時に「どの方にどこをお願いするか」という配置を考える。「この人はアクションが持ち味だからこのカットをお願いしたい」とか、「ここにはどうしてもあの人を入れたい」とか、その話数が作品の中でどういう回なのかを把握して、配置プランを考えてお願いしていく。そのプランによってその回の完成度が大きく変わるので、そこが面白い。思ったようにハマってくれると嬉しいしやりごたえがあります。制作進行でしか味わえない醍醐味で、制作進行が「話数のプロデューサー」と言われる所以です。
私自身、キャリアのスタートは制作進行です。延べ3年ほど制作進行を務めて、設定制作、制作デスク、プロデューサーとなっていきました。
――ボンズに制作進行職で就職を希望される方に、必要な心構えなどはありますか?
大薮芳広:会社説明会でも必ずお伝えしているのですが、ひと言でアニメの会社と言っても、実際にはさまざまな仕事があります。テレビ局、広告代理店、パッケージメーカー、音楽会社、出版社のメディア部など、いろんな関わり方の会社があります。その中で、アニメ制作会社というのは、アニメが作られる最も近いところで仕事をしています。ものづくりの喜びをすごく体感できるし、その反面、ものづくりの辛さも味わいます。ものづくりが楽しめる人や現場に近いところで仕事をしたい人に志望してほしいなと思います。
――では、その上で具体的に求められる制作進行の資質とはどのようなものでしょうか?
大薮芳広:大きくはふたつあります。まず、ものづくりに努力や情熱を惜しまない人。モチベーション高く持ち続けられる方ですね。情熱がないと自分が続けていく推進力にならないのかなと思います。例えば特定のアニメ作品が好きで、それに関わりたいということだけだとモチベーションとして続きにくい。制作会社では、好きな作品や所属スタジオを選べるわけではないし、もっと言えば、作品によって作り方も微妙に違っていて、必要になる対応が違ってきます。だからこそ多くの作品を経験する方がスキルを磨けるし、それが自分の未来のためになる。特定の作品だけではなく、「映像を作る」ということに対して高い熱意を持っていることは非常に大事だと思います。映像づくりそのものが好きであれば、自分がどんな作品を担当しても愛着が湧いて好きになる、というところもあります。
ふたつめは対応力ですね。それは挨拶ができるという基本もあるんですけど、制作進行では折衝や説得力が必要になる場面もあります。そのため、重要なのはそういったコミュニケーション力を含めた対応力と考えています。制作進行においてはマルチタスクが求められるので器用さもあれば良いのですが。
――折衝と説得力ですか。
大薮芳広:はい。クリエイターの方は感性を研ぎ澄まして高い熱量でお仕事をされているので、こだわりの強い方も多いです。制作進行はそうした方々と渡り合いつつ、作品に落とし込んでいくことが仕事になります。先ほど、プロデューサーが経験を積むと「人間力」が上がるというお話しもしましたが、制作として経験を積んで人間力が上がると、クリエイターの方に作業の説明をするだけではなく、「あなたにはこういう理由でこうしてほしい」まで伝えられるようなります。制作には、クリエイターと向き合って渡り合える説得力が必要ですし、いろんな経験を積むことで人間力が上がれば、自らの力で良いフィルムに落とし込んでいける。そこも仕事の楽しさだなと思っています。